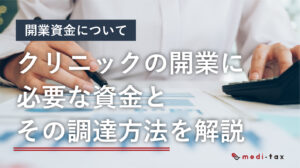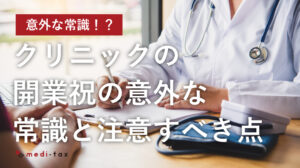記事カテゴリー
タグ一覧
コラム
【徹底解説】医師以外でもクリニックは開業できる!
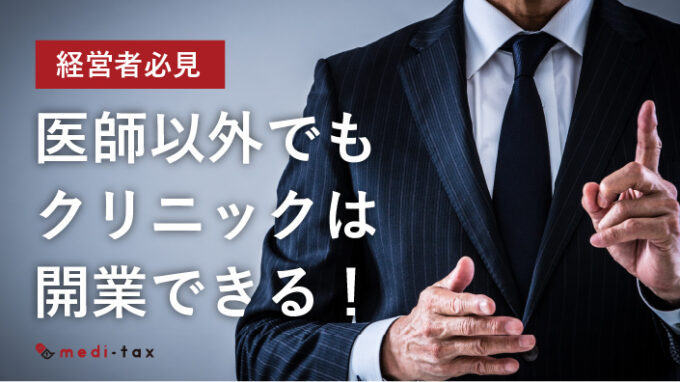
クリニックの開業と聞けば、一般的には勤務医が独立して開業する、あるいは親や親族のクリニックを継承するイメージでしょう。
実は医師以外でもクリニックを開業する方法が存在していて、その目的や方法はいくつかのパターンに分かれます。
本記事は、医師資格のない人物がクリニックを開業する方法や、そのメリットとデメリットを多角的に解説する内容です。

医師以外の方がクリニックのトップになるパターンとは?

社会活動の多くには「本音と建前」というものが存在し、医療法では営利を目的とする病院・クリニックの開設は原則認められないことになっています。
これには医療行政や医師会の思惑も絡んでいて、保険調剤薬局を株式会社などの営利法人が営んでいることが非難の対象になっているわけです。
それは置いておくとして、医師以外がクリニックを開業(経営)する目的がどこにあるのか考えてみましょう。
医師がクリニック経営に自信がないケース
医師として独立することに興味があったとしても、クリニック経営に今一つ自信が持てない方もいるのではないでしょうか。
煩わしい開業準備や資金計画などを人に任せ、自分は医師として医療に専念したいというのも考え方の一つです。
医師がクリニックを開業するとき、個人開業するのが一般的ですが、その場合「開設者=管理者」となるので、開設者の地位に非医師が付くことは無理でしょう。
ただ、中には医師が個人クリニックを開業して、実質的な経営者は医師の配偶者というケースも無いことはありません。
しかし、その場合であっても許可上の開設者(経営者)は、医師本人ということになります。
資格はないがクリニックを経営したいケース
クリニックを開業する医師の考えではなく、非医師がクリニックを経営したいと思う理由は何が考えられるでしょうか。
多くの場合は、経済的利益を求めているケースがほとんどで、以下の2つのパターンのいずれかになります。
- クリニック経営で大きく利益を上げたい
- クリニックの周辺事業で利益を上げたい
このなかで1の場合は、クリニック経営を医師の親族以外が行うと、多くのケースで上手くいかないようです。
このスタイルでは、結局のところ医師は「雇われ医師」と変わらないことになり、モチベーションを保てなくなるでしょう。
また医師と実質的な開設者の関係がこじれ、医師が退職した途端ビジネスモデルが破綻します。
また2のケースは比較的多く見られるもので、クリニックの経営が主目的ではなく周辺事業で利益を上げることが目的です。
この場合でもクリニックはサブ的な扱いになるので、医師としては微妙な立場だといえるかもしれません.
医師以外がクリニック経営者になる4つのパターン

あまり一般的ではない非医師によるクリニック開業ですが、そのようなケースが無いわけではなく、いくつかの方法で医師以外が経営者になることができます。
そこで医師以外がクリニック(医療法人を含む)経営者になることができる4つのパターンと、そのための手順などについて見ていくことにしましょう。
MS法人として企業が運営をサポートする
MS法人とは「メディカル・サービス法人」の略称で、実態としては株式会社などの営利法人です。
届け出上はMS法人の名前が出ることはなく、「クリニックの陰に隠れた存在」と表現した方がイメージしやすいでしょう。
ただ、好意的に捉える考え方もあり、通常の医療法人が行うことのできない営利事業をMS法人が担ったり、会計・保険請求・医薬品販売・人材派遣など、医療行為以外の事業をMS法人に委託したり、業務効率化を図ることができます。
このMS法人ですが個人クリニックの場合、節税以外ほとんど利用価値はないといえます。
なぜなら、個人クリニックは営利目的の活動が認められているので、わざわざMS法人を利用するメリットは少ないからです。
一方で医療法人の場合は営利事業を禁止されているので、MS法人を活用することで不動産の貸し付けや医療機器の販売など事業を展開することができます。
このMS法人を利用したクリニックへの経営参加ですが、「事実上の経営参加」という手法なのでMS法人を設立する必要はないことにお気づきでしょうか。
ただ、医療法人との組み合わせはメリットが大きいので、医療以外の周辺事業への拡大を考えているのなら前向きに検討すべき手法です。
医療法人を設立して開業する
医療法人は病院・クリニックの開設・所有を目的とする法人ですが、医師免許がなくても設立が可能です。
医療法人の最高意思決定機関は「社員総会」で、その過半数を押さえることで非医師でも実質的に病院・クリニックを経営できることになります。
医療法人の理事長については「医師もしくは歯科医師である理事から選定しなければならない」と医療法に定められていますが、都道府県によっては例外的な認可によって非医師が理事長になれる場合があります。
ただ、そのハードルは高いので理事の過半数を押さえる方法が現実的でしょう。
医療法人の設立は「医療法人設立認可申請書」を作成して、主たる事務所の所在地の都道府県へ提出し認可を受けます。
手続きも煩雑なので、医師による通常のクリニック開業でも最初から医療法人を設立するのは一般的ではありません。
一般社団法人を設立して開業する
2008年に施行された「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律」により、一般社団法人が病院・クリニックを開設できるようになりました。
一般社団法人でクリニック等を開設すると、医療以外の業務ができないなどの制限がなくなり、代表者が医師である必要もありません。
非常に自由度の高いクリニック経営が可能になりますが、あまり開業事例がないことから管轄保健所によって個人での開業実績がないと認めない場合があります。
とくにクリニックの開設許可では、一般社団法人の非営利性を細かくチェックされる場合があり、そもそも開設を認めていない地域もあるので注意が必要です。
医療法人を買収する(M&A)
非医師が新規で医療法人を設立するには障害も多いので、既存の医療法人を買収するM&Aをすることで社員として経営に参画する方が現実的です。
医療法人には、「出資持分あり」と「持分なし」の2種類があり、平成19年(2007年)4月1日以降「持分あり」の医療法人は設立できなくなっています。
「持分あり」の医療法人では、財産である出資持分を買い取ることで買収することが一般的です。
また「持分なし」の医療法人では、出資持分の代わりに基金を買い取ります(基金拠出型医療法人の場合)。
いずれの場合も議決権の過半数を占めることで、実質的な病院・クリニック経営に参画することになります。
いずれにしても高めなハードル
日本においては、クリニックや病院の開設は医師の資格を持った者が開設する前提の制度設計になっています。
そのためイレギュラーなケースといえる非医師による病院・クリニックの開設は、制度上も手続き上もハードルが高いのが現実です。
ここで個人クリニック、あるいは医療法人で病院等を経営するための要件を整理して、その違いや手続きについて確認しておきましょう。

| 個人 | 医療法人 | |
| 施設の種類 | 病院・クリニック(診療所) | 病院・クリニック(診療所) |
| 開設者 | 医師 | 法人 |
| 管理者 | 医師 | 医師 |
| 許認可の有無 | 届出のみ | 都道府県知事の許可 |
| 登記 | なし | 必要 |
| 経営できる診療所数 | 1ヵ所のみ | 複数分院の開設が可能 |
| 営利事業 | とくに制限なし | 禁止されている |
こうして比較してみると、医師が開業するときの将来像をしっかり考えておくべきことが分からないでしょうか。
自由度が高い個人クリニックに対して、規模の拡大など事業拡大のためには医療法人がメリットが大きいといえます。
実質的なクリニック経営者になるケース

ここまでは表面的な経営形態を法律に合わせることを主眼に解説してきました。もうお気づきのこととは思いますが、クリニック経営は表面上の要件をクリアしさえすれば自由なものです。
ここからは、表向きの経営とは違った合理的な判断について詳しく考えることにしましょう。
確かな診療を行う医師とプロ経営者のタッグ
医師のなかでもカリスマ的な医師の存在を意識することはないでしょうか。医師から見ても尊敬できる方はいるものです。
例えば、明らかに「医療にしか興味のないプロの医師」がいたとして、そのような医師が自分の儲けだけを追求するでしょうか。
断言はできないものの、そのような「理想の医療」を求める医師であれば、経営を任せられるプロの経営者とタッグを組むメリットはあります。
ただ、一般的には医師が開設者で管理者という開業が普通なので、よほどのことがない限り医師が開業したほうが全てにわたりスムーズにいくでしょう。
ただ、人事を含めた経営は余計なストレスになるかもしれないので、経営を任せるというより「経営相談できるパートナー」を見つける方が正しい選択です。
他人同士の組み合わせでは大きなリスクも
医師以外のクリニック経営は、医師と非医師の協業となりますが、この共同経営というスタイルはメリットだけではなく大きなリスクも伴います。
これはクリニック経営以外でもよく聞かれる話で、以下の点で「共同経営は失敗しやすい」と言われています。
これらのリスクは、血縁関係のない他人同士の共同経営でより顕著に見られるリスクです。
また、一度共同経営を始めてしまうと、一方のわがままで関係を解消しづらいというデメリットも考えられます。
もちろん、自分にはないスキルや経験を持つ人と協力するといったメリットもありますが、(医師側から見て)非医師が医師資格を利用するという側面が大きいことを自覚しましょう。
クリニック経営に自信がないならコンサルの活用を
クリニックの開業には興味があっても、「クリニック経営に今一つ自信が持てない」や「開業までの手続きや資金調達が心配」という医師の方は、コンサルタントの活用を視野に入れましょう。
クリニックを開業するためには、勤務医として働いているうちから多くの準備があり、それを確実に進める必要があります。
また、それまであまり経験していないような「経営者の視点」が求められ、資金調達と開業後の円滑な経営のため事業計画書なども必要です。
開業後もクリニック経営者として診療以外の業務もこなさなければならず、そんなことを想像するだけで及び腰になってしまわないでしょうか。
このような業務を避けるために非医師と共同経営する以外にも、外部のコンサルを活用する選択肢もあります。
共同経営などと違い経営権の心配をすることもなく、委託する業務を絞って任せることができるので、結果的に経済的だといえるでしょう。
クリニック開業と医師資格の関係
クリニックの開業は、ごく一般的な医師による開業が成功の近道ですし、経営効率の面でも合理的です。
とはいえ非医師との協業が必ずダメだと断言できるものでもなく、ケースバイケースの判断になります。
そこで、クリニック開業にあたって知っておくべき「医師の強み」と、医師ではないものがクリニック経営を志すときの注意点を考えてみましょう。

医師免許の強みを知りましょう
釈迦に説法かもしれませんが、医師免許を取るまでの道のりは受験するまでが大変だったのではないでしょうか。
国家資格に合格し「医師免許」を取得すると臨床医としてだけではなく、以下のように様々な活躍の場が考えられます。
| メディカルドクター | 製薬企業や医療機器メーカーなど企業で働き、新薬開発における臨床試験や安全性の審査、販売支援、医療機関への最新医薬情報の提供などを行う。 |
| 医系技官 | 厚生労働省で働く国家公務員で、保健医療制度の企画・立案に専門的見地から関わり、法案や予算案、制度を作成する。 |
| 保険会社の社医 | 生命保険会社などで保険加入者の審査を行う。審査以外にも加入の妥当性を判断する引受査定や、保険金支払時の正確性・公平性などを評価する支払査定も社医の仕事です。 |
| 産業医 | 企業において専門的立場から労働者の健康管理を行う。身体面だけでなくメンタル面の不調にも気を配る必要があるので幅広い医学的見識が求められます。 |
| 介護老人保健施設 | 高齢者の健康管理や健康指導だけでなく、施設長として人材・財務管理などの施設運営、入所者や家族への相談対応もおこないます。 |
| 矯正医官 | 刑務所などの矯正施設で医療処置を行う。受刑者の病気・怪我の診療や入所時と定期の健康診断を実施し、釈放後の支援、再犯防止まで視野に入れることが必要です。 |
| 公衆衛生医師 | 自治体の保健所や保健センターで働く公務員で、地域住民の健康増進や健康危機管理に関わる仕事に従事します。 |
これら以外にも、医師としての専門性を活かして民間企業やコンサルタントとして働くなど、非常に多様性の高い資格だといえるでしょう。
それだけに、医師免許を活用する方法は慎重に考えるべきで、クリニック開業に自信がない場合など「雇われ院長」という手段も考えられます。
これは医療法人の運営する分院などで管理医師として働くもので、勤務しながら経営のノウハウを学べるメリットもあり、検討に値する選択肢です。
もし無資格でクリニック経営を志すなら知っておくべきこと
医師免許を持っていなくてもクリニック経営を志すのは、簡単にできるものではありません。
本記事でも解説しているいくつかの方法はあっても、医師が開業する場合に比べて運営コストは増え、デメリットの方が多いのというのが現実です。
しかし、医療を通して社会に貢献しようと思うなら、志を共有できるしっかりとしたパートナーを探すことが第一歩になります。
そのうえで必要なことは、クリニックに関連する周辺事業で基礎を固めることで、財務基盤が強固ならクリニックサイドから協力を申し込まれることも考えられるでしょう。
いずれにしても非医師がクリニック経営に関わるには、ぶれない強い意志が必要です。
クリニック開業の様々な選択肢はmedi-tax株式会社にお任せください
医師がクリニックを開業する方法や進め方には実に様々な選択肢があり、100%成功が保証されているものでもありません。
その中でも、リスクを下げる方法は存在していて医業に強みを持つmedi-tax株式会社であれば、税理士事務所の視点から多くのノウハウをご提供できます。
クリニック開業する際に必要な、物件の選定から資金調達・開設に必要な各種手続きの開業支援から、開業後最も重要なキャッシュフロー周りを管理する税務顧問までをサポートさせていただいているので、是非当社の無料セミナーをご活用ください。
最後に
クリニック・病院の開業で非医師が経営者になるのは一般的なことではありませんが、その実例はあり非合法的なものでもありません。
上手く双方の強みを組み合わせれば、非常に大きなシナジー効果を生む可能性があります。
一方でリスクもある開業手法なので、このような事案がある場合は専門家へ相談してから進めることが重要です。