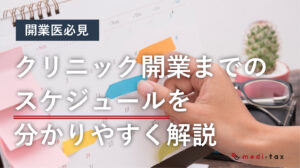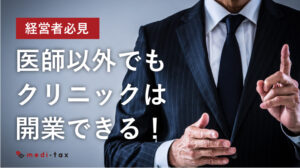記事カテゴリー
タグ一覧
コラム
クリニックの開業に必要な資金はどれくらい?疑問や用建ての解決策
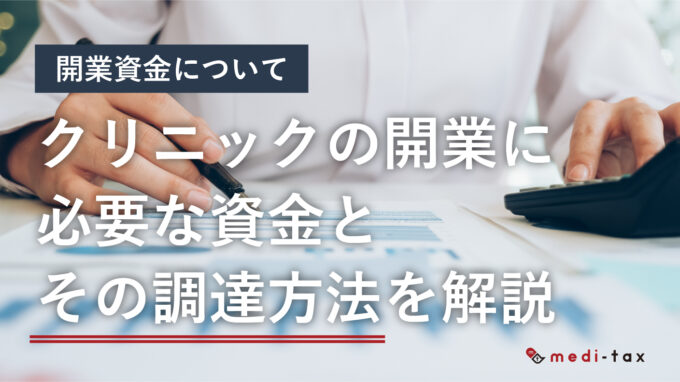
クリニックの開業を考えた場合、避けて通れないのが「開業のため必要な費用」と、その調達方法です。
本記事では、クリニック開業に必要な資金の内訳を診療科ごとにピックアップし、自己資金と借入金の考え方、また資金調達方法について解説します。
クリニック開業に必要な資金の内訳
クリニック開業にかかる費用といえば、真っ先に開業場所の確保に関わるものや医療機器の購入が思い浮かぶと思います。
しかし開業資金には、意外と多くのものが含まれオープン後も視野に入れた計画を立てないと、安定経営がおぼつかなくなるものです。
まずは、クリニック開業にあたり必要になる資金の内訳を、大まかな分類別に確認することにしましょう。
クリニック開業場所の取得資金
クリニックを開業するためには「場所」を探して、開院できるだけの設備投資をすることが必要です。
開業物件を大きく2つに分けると、土地や建物を購入して自己所有するケースと、賃貸物件にテナントとして入居するケースとなります。
もちろん前者の方が多額の開業資金が必要になりますが、全く新規に自己所有物件で開業するケースは少数派です。
日経メディカルが行ったアンケートによると、クリニック開業を検討している医師の全年代で「テナントで開業を希望する」の割合が高くなっています。
また20代で開業を視野に入れている方では「親または親族の診療所を引き継ぐ予定」が多く、当てがあるから若くして独立を視野に入れているのでしょう。
テナントで開業する場合、エリアによる違いが大きく都心部になるほど必要資金が多くなります。
ただ、戸建てや医療モールよりも初期費用は安めで済むので、開業エリア選びとともに難しい判断となるでしょう。
テナントで開業するとき、物件の取得にかかる費用内訳は次の通りとなり、家賃が高いほど必要資金は大きくなります。
| 内訳 | 備考 |
| 敷金(保証金) | 賃貸借契約に際し、賃料等の契約上の債務を担保するために預ける費用。月額賃料の6~12ヶ月が相場。 |
| 礼金・仲介手数料 | ・礼金:賃貸借契約の謝礼として賃貸人に支払う(賃料の1~2ヶ月)。地域によってはないところも。・仲介手数料:不動産会社に支払う手数料(賃料の1ヶ月分) |
| 前家賃 | 賃貸借契約から開業(内装工事等の準備期間)までの家賃。準備期間によって変動。 |
実際にクリニックを開業してみなければ医業収入がいくらになるか正確には分かりませんが、クリニック経営で適正とされる家賃は収入の6~8%程度とされています。
開業に向けては事業計画を検討されると思うので、見込収入に対して家賃がどうなのかも考えてみましょう。
内装や医療機器などの設備資金
クリニックの開業で最も多額の資金を要するのが「内装工事」ですが、クリニックを訪れる患者の印象を左右する重要なポイントでもあります。
また、クリニックの内装工事は医療法などの制約を踏まえたものでなければ、保健所から開設許可が下りない可能性もあるので注意が必要です。
内装工事にかかる費用は、開業するクリニックの面積と工事内容によって大きく変わってきます。
またテナントが居ぬき物件で工事範囲が限られている場合と、ゼロから改装工事をする場合でも違うことは理解できるでしょう。
基本的に内装工事代は、(工事をする床面積 × 工事の坪単価)でおおよそ把握できます。
ではクリニックの開業に必要な面積や、工事の単価はどれくらい見積もっておけばよいのでしょうか。
クリニックの開設に必要な床面積は医療法では診察室が9.9㎡以上、待合室が3.3㎡以上とされていますが、診療科ごとの面積は以下の広さが一般的です。
| 診療科 | 必要な床面積(目安) |
| 内科 | 30~50坪(約99~165㎡) |
| 小児科 | 30~40坪(約99~132㎡) |
| 外科 | 50~70坪(約165~231㎡) |
| 耳鼻咽喉科 | 30~40坪(約99~132㎡) |
| 眼科 | 35~40坪(約115~132㎡) |
| 皮膚科 | 25~50坪(約82~165㎡) |
| 婦人科 | 35~45坪(約115~148㎡) |
上記の面積はあくまで目安なので、医療機器の種類や手術を含めた提供医療によって変わってきます。
次に工事の坪単価ですが、悩ましいことに費用を掛けようと思えば青天井に上がっていくもので、検討段階でかなり頭を悩ませることでしょう。
最低限の内装で良ければ30~50万円/坪で済むかもしれませんが、現実的には60~100万円/坪が相場だと言われています。
入居する物件の電気容量や給排水設備などによっても大きく変動するので、物件選びと密接に関わってきます。
また医療機器の選定も理想の医療を追いすぎると、結果的に多額の設備投資となってしまうので、予想される患者層や開業後の収入を慎重に予想することが重要です。
開業準備資金
クリニック開業へ向けて準備している期間には、物件や工事だけではなく様々な必要経費が発生し、それを支払わなければなりません。
ざっと考えただけでも以下のような支出があるので、開業するクリニックの立地や規模などを考え、開業準備資金として用立てておくことが必要です。
| 内訳 | 細目 |
| OA機器・システム導入 | 電子カルテ・レセコン・PC・予約システム等の導入費用(リース契約の場合が多い) |
| 医薬品・医療消耗品 | 診療に必要な医薬品、消耗品など |
| スタッフの採用・研修 | 採用のための広告費や人材紹介会社への紹介手数料等 |
| 集患のための広告費 | ホームページ作成、SNSの運用、看板の設置など |
| 医師会などへの加入費 | 地域の医師会や団体への加入金 |
| その他消耗品等の購入 | 事務用品やトイレ用品など一般の消耗品 |
OA機器や通信機器は高額になるので、リース契約での導入が一般的ですが、場合によっては中古品のリユースも検討しましょう。
運転資金
クリニックを開業してからは、運営を続けるためのランニングコストが発生し、それを支払うことが出来ないと経営が成り立たなくなります。
診療報酬が支払基金から入金されるのは、請求後約2ヶ月後となるので少なくともその間は支払う一方です。
それに加え、クリニックの開業直後から収支がプラスになるという保証はないので、経営が軌道に乗るまでの資金を確保しなければなりません。
つまり開業時に用意すべき運転資金は、開業後いつまでにクリニックを黒字化するか明確な目標を立て、そこまでの支出超過を賄うだけの金額が必要です。
資金不足が目に見えてくると、本来力を入れるべき本業への集中力も削がれてしまうので、しっかりとした事業計画のもと、余裕のある運転資金を考えておきましょう。
クリニック開業に必要な資金を診療科目別に知りましょう

クリニック開業に必要な資金は、クリニックの診療方針や開業エリアなどによって大きく変わってきます。
あまり細分化していくときりがないので、都市部にテナント開業するケースを念頭に、診療科ごとの開業に必要な資金を見ていくことにしましょう。
内科
内科領域のクリニックは一般内科として開業するのか、専門医の資格をお持ちで循環器内科、呼吸器内科、神経内科と単科標榜(もしくはそのような医療を提供する)をして開業するのかで、必要な資金が変わってきます。
特に消化器内科として開業する場合、回復室やトイレが複数必要なので50坪ほどの広さが必要になり、初期投資が増えるでしょう。
| テナント取得・内装工事 | 2,000~3,500万円 |
| 医療設備 | 500~2,000万円 |
| 開業準備資金 | 1,000万円 |
| 運転資金 | 2,000万円 |
| ※開業資金合計 | 5,500~8,500万円 |
(注:金額はあくまで一般的な参考額です)
耳鼻咽喉科
耳鼻咽喉科は子どもの中耳炎から頭頸部腫瘍に至るまで、非常に多様な疾患を扱う診療科ですが、診療内容や手術の有無によって開業費に違いが見られます。
ネブライザーやファイバーなど医療機器の価格とメンテナンス料も大きいので、医療コンセプトを明確にしておくことが必要です。
| テナント取得・内装工事 | 2,500~3,000万円 |
| 医療設備 | 1,000~2,000万円 |
| 開業準備資金 | 1,000万円 |
| 運転資金 | 2,000万円 |
| ※開業資金合計 | 6,500~8,000万円 |
(注:金額はあくまで一般的な参考額です)
皮膚科
皮膚科としてクリニックを開業する場合、保険診療をメインとして考えれば2つの診察室と1つの処置室で十分なため、25~30坪の広さで開業が可能です。
自由診療のレーザー機器、美容系機器を導入することは、クリニックの経営が軌道に乗るまではオススメできません。
他の診療科と比べても広い年齢層の患者が利用するので、目につきやすい立地が重要だといえます。
| テナント取得・内装工事 | 2,000万円 |
| 医療設備 | 500万円(自由診療を行う場合は別途必要) |
| 開業準備資金 | 800万円 |
| 運転資金 | 1,500万円 |
| ※開業資金合計 | 4,800万円 |
(注:金額はあくまで一般的な参考額です)
整形外科
整形外科の開業は診療報酬体系を理解した開業戦略が必要で、無駄な医療機器に設備投資しすぎないことが重要です。
むしろクリニックの評判を高めるためには、優秀な理学療法士の採用など、運転資金の余裕が必要なのかもしれません。
| テナント取得・内装工事 | 2,000~3,000万円 |
| 医療設備 | 1,500~2,000万円 |
| 開業準備資金 | 1,000万円 |
| 運転資金 | 2,000万円 |
| ※開業資金合計 | 6,500~8,000万円 |
(注:金額はあくまで一般的な参考額です)
泌尿器科
全医師の中でも泌尿器科医は少なく、泌尿器科でのクリニック開業はライバルが多くないといえます。
一方で泌尿器科に対する「受診するのが恥ずかしい」というイメージから、クリニック内の待合室や動線を男女で分けるなどの工夫が重要で、ある程度の広さが必要です。
| テナント取得・内装工事 | 2,000~3,000万円 |
| 医療設備 | 2,000万円 |
| 開業準備資金 | 1,000万円 |
| 運転資金 | 2,000万円 |
| ※開業資金合計 | 7,000~8,000万円 |
(注:金額はあくまで一般的な参考額です)
脳神経内科
他の診療科と比べまだまだ認知度が低い脳神経内科ですが、本格的な高齢化社会で今後のニーズは大きくなるでしょう。
医療機器は最低限の導入で事足りますが、リハビリの算定を考えるとバリアフリーで50~60坪の広さが必要です。
| テナント取得・内装工事 | 3,000~4,000万円 |
| 医療設備 | 800~1,200万円 |
| 開業準備資金 | 1,000万円 |
| 運転資金 | 2,000万円 |
| ※開業資金合計 | 6,800~8,200万円 |
(注:金額はあくまで一般的な参考額です)
脳神経外科
脳神経外科の開業資金は、CTやMRIなどの高額な医療機器を自前で持つかどうかで天と地ほどの差が出ます。
画像診断センターにアクセスが良いなら、そこを活用するという方法も考えられるので、事業計画の詳細な検討が何より重要です。
開業資金が3億に迫るような事業計画は、見直しが必要なのかもしれません。
| テナント取得・内装工事 | 2,500~3,000万円 |
| 医療設備 | 2,000 ~1億8,000万円 |
| 開業準備資金 | 1,000万円 |
| 運転資金 | 2,000万円 |
| ※開業資金合計 | 7,000~2億4,000万円 |
(注:金額はあくまで一般的な参考額です)
小児科
小児科クリニックは、ファミリー層の多いエリアでの開業と、アクセスの良さや駐車場・駐輪場の確保がポイントです。
医療機器などの設備投資は少なく済みますが、スタッフの質が評判に直結するので、人材確保の経費などランニングコストが嵩むかもしれません。
| テナント取得・内装工事 | 2,000~3,000万円 |
| 医療設備 | 500 ~1,000万円 |
| 開業準備資金 | 1,000万円 |
| 運転資金 | 2,000万円 |
| ※開業資金合計 | 5,500~7,000万円 |
(注:金額はあくまで一般的な参考額です)
産婦人科
婦人科クリニックの開業は、医療コンセプトを明確にしてから物件や医療機器を選ぶことがポイントです。
お産や中絶を扱うとなると開業のハードルは一気に上がります。また不妊治療も最初から高度な治療を行うとなると設備投資も増えるでしょう。
もし女性医師で婦人科クリニックを開業するなら、それ自体が強みになるので、広告に力を入れることもオススメです。
| テナント取得・内装工事 | 2,000~3,000万円 |
| 医療設備 | 1,000 ~1,500万円 |
| 開業準備資金 | 1,000万円 |
| 運転資金 | 2,000万円 |
| ※開業資金合計 | 6,000~7,500万円 |
(注:金額はあくまで一般的な参考額です)
精神科・心療内科
全診療科のなかで開業資金が一番少なく済むのが精神科・心療内科ですが、近年は開業数も右肩上がりで競争の激しい診療科です。
開業にあたってのポイントはインターネットでの広告戦略で、ホームページの作成とSEO対策に力を入れましょう。
| テナント取得・内装工事 | 1,000万円 |
| 医療設備 | 200 ~500万円 |
| 開業準備資金 | 800万円 |
| 運転資金 | 500~1,000万円 |
| ※開業資金合計 | 2,500~3,300万円 |
(注:金額はあくまで一般的な参考額です)
美容皮膚科と美容外科
美容皮膚科や美容整形は自由診療が流行りとなっており、開業資金も他の診療科と比べると高めな傾向にあります。
特に医療機器の準備では「欲張るほど設備投資が過大になる」傾向があり、回収するためには開業時やその後の広告戦略が重要です。
特殊性が色濃いので、この分野に精通したコンサルタントの利用を考えましょう。
| テナント取得・内装工事 | 2,000~3,000万円 |
| 医療設備 | 2,000 ~4,000万円 |
| 開業準備資金 | 1,000万円 |
| 運転資金 | 2,000万円 |
| ※開業資金合計 | 7,000~1億円 |
(注:金額はあくまで一般的な参考額です)
開業にあたっての自己資金と借入

診療科ごとの開業資金の目安は把握できたとして、問題はそれをどのように用意するかです。
在宅医療や精神科・心療内科などであれば大きな負担も伴いませんが、一般的なクリニックの開業では数千万円の資金が必要になります。
そこで、開業資金を用立てるためのいくつかの方法について考えてみましょう。
自己資金はいくらあればいいの?
クリニックの開業資金のうち、その全てを銀行借入で賄うのは現実的ではありません。
金融機関も融資するための条件として、開業資金の一部を自己資金で賄うことを求めていることが一般的です。
では、どの程度の自己資金を持っていれば良いのでしょうか?比較的多いのが「必要資金の1~2割は自己資金があること」という金融機関です。
つまりクリニックの開業資金が8,000万円だとしたら、800~1,600万円の自己資金がなければ融資の実行も覚束ないでしょう。
ただ、自己資金全てをクリニック開業につぎ込んでしまうと、クリニック経営が軌道に乗るまでの生活費に困るので、それを確保したうえで投資できる金額が「自己資金」の定義です。
クリニック開業にあたって資金を貸してくれそうなところ
クリニック開業を考えた場合、融資を申し込む先としてはいくつかの金融機関が考えられます。
開業医の利用が多いのは次の金融機関で、その特徴をよく把握しておきましょう。
日本政策金融公庫
クリニックを開業するとき、資金調達先として真っ先に検討すべき金融機関が「日本政策金融公庫」となります。
日本政策金融公庫は、個人での創業や中小企業の経営支援を行う政府系の金融機関で、低い固定金利で融資を受けられるのが魅力です。
クリニック開業では、創業・スタートアップを支援する「新規開業資金」が利用でき、融資限度額は7,200万円(うち運転資金4,800万円)となります。
返済期間は20年以内(運転資金は10年以内)と長めなのも魅力ですが、審査が難しく時間もかかることがデメリットです。
参考:日本政策金融公庫
医師会・地方自治体のローン
各都道府県の医師会の多くで、医師信用組合や地方自治体と連携しクリニックの開業に特化した開業支援ローンを用意しています。
当然のように医師会への加入が条件ですが、融資限度額も日本政策金融公庫より多く、医師にとっては使い勝手の良い金融商品だといえるでしょう。
また自治体制度融資も選択肢の一つで、創業支援、産業振興などの経済発展のために低金利で融資を活用できます。
多くの場合、都道府県や市区町村などの自治体と信用保証協会と金融機関による三者協調により成り立っていている制度です。
参考:三井住友銀行開業医ローン
これらの金融機関の利用にあたっては、様々な書類の作成やその裏付けが必要になるので、クリニック開業に強みを持つコンサルタントや税理士の利用も検討してみましょう。
事業資金を借りるために必要な事業計画書
金融機関へ事業資金の融資を申し込む場合、開業までに必要な資金の見積もりと、開業後数年先までの収支・資金計画を盛り込んだ「事業計画書」が必ず必要です。
いくら社会的信用の高い医師とはいえ、何も持たずに金融機関へ行き「お金を貸してください」といっても貸してくれるわけはありません(カードローンなら別ですが・・・)。
事業計画書の作成は、クリニック開業を考え始めた早い段階から着手すべきで、金融機関を納得させるだけの正確性が求められます。
つまり、早い段階から専門家の意見を取り入れながら計画を進めることが、クリニック開業を成功に導くポイントです。
無理のない返済計画を考えましょう
金融機関から開業資金を借りると、返済期間は10~20年で設定されることが一般的です。
開業時の年齢にもよりますが、金利負担を気にするあまり短すぎる返済期間にすることはオススメできません。
とくに開業後1~2年間は、クリニック経営が軌道に乗るまで資金的な余裕はあまりないと思われます。
ランニングコストの支払い、あるいは借入返済を滞れば、それはクリニック経営の危機となってしまうので、あくまで無理のない返済計画が重要です。
クリニック経営が順調になり、資金に余裕ができたら繰り上げ返済も可能なので、お金の悩みを発生させないようにしましょう。
クリニック開業で失敗しないためのポイント

クリニックの開業で失敗しないためのポイントは、どのような業種の開業とも同じような傾向があります。
その中でも特に押さえておきたい点について考えてみましょう。
初期投資は欲張らないこと
クリニックの開業では、少なからず「理想の医療」や「このようなクリニックにしたい」という希望を持たれることだと思います。
しかし多くのクリニック開業では、スタートと同時に千客万来とはいかないのが現実です。
理想にこだわるあまり、高額物件を選んだり高価な医療機器をたくさん導入したり、初期投資を増やしすぎると、それに比例して借入金額も増えてしまいます。
そうなると開業後の資金繰りが苦しくなることになり、クリニック経営が軌道に乗るまでのハードルが上がってしまうので、あまり欲張らないことが失敗しないためのポイントです。
クリニックの見通しを考えるときに、軌道に乗せるまでのステップと、その後経営を拡大させるステップを分けて考えると良いかもしれません。
値下げ交渉は恥ずかしいことではありません
どんな設備投資や買い物も、相手の言い値で契約してしまうことは大きな損失になってしまいます。
どの業者も先生方をおだてあげ、少しでも高い金額で買わせようとしているのが現実です。
実際にMRIの納入価格が2倍近く違ったという事例も見られるので、正々堂々と値下げ交渉をしましょう。
考えようによっては、値下げ交渉をすることもクリニック経営の一環なのです。
専門家の力を利用する
クリニックの開業は、お金の話を切り離すことができません。また事業計画の作成や、その前段階の医療圏調査など面倒な作業が山ほどあります。
もちろん全てを一人で進めることは不可能ではありません。ただ、勤務医として働きながら並行してこれらの作業をするのは現実的ではありません。
そこで活用すべきは、クリニック開業に強みをもつ専門家の活用で、medi-tax株式会社にご依頼いただけたら豊富なデータと経験をもとに必ずお役に立てます。
確かな成功を収めたいと思うのであれば、ぜひmedi-tax株式会社の無料相談をご利用ください。
最後に
クリニックの開業には多くの資金が必要になり、その準備をすることも大変な作業となります。
事業承継で既存クリニックを引継ぐ場合は別ですが、それ以外のケースでは早めの準備と、コンサルタントの活用が不可欠です。
もしクリニック開業の可能性を少しでも考えることがあったら、その段階に一度専門家へ軽い気持ちで相談してみましょう。
万が一それが無謀な考えだと気付けたとしたら、それはそれでプラスになることです。
medi-tax株式会社にご相談頂けたら、進むにしても考え直すにしても必ずお役に立てるので、「開業も良いかなぁ」という段階からご利用ください。