記事カテゴリー
タグ一覧
コラム
【開業医必見】クリニック開業の失敗の落とし穴を避ける方法

勤務医と比べ高収入を見込めるクリニックの開業ですが、必ず成功するという保証はありません。
しかし、成功ではなく「失敗の落とし穴」を避ける方法があるので、逆説的ですが”その方法”を知ることが成功への近道になります。
本記事は、 開業をお考えになっている医師の方が避けなければならない失敗の原因を考察し、前へ一歩踏み出すお役に立つ内容となっております。
【よくあるクリニック開業の失敗】一般的な落とし穴を理解する
医師が開業したときの失敗率は他の業種に比べて低い傾向がありますが、これからの日本で同じような状態が続くとは考えない方が良いでしょう。
ただ、医療のニーズは未来永劫無くなるものではないので、「失敗さえしなければ成功」だとも言えます。
まずクリニック開業の失敗とは、どのようなことを指すのか正しく理解し、その具体的な事例を知ることで、避けるべき落とし穴を理解しましょう。
失敗の定義とその影響
クリニックを開業したとして、それが失敗したといわれる状態にはいくつかの定義があります。
医師が開業したクリニックといえども、それは個人事業に他ならないので、赤字経営や資金繰りに窮したことによる廃業は「明らかな失敗」でしょう。
大都市圏ではクリニックの新規開業が多く、激しい競争から思うように集患できないクリニックも見受けられます。
患者様が来なければ事業として成り立つはずもなく、運営に係るコストも払えず廃業に至ってしまうのです。
これは経済的に成り立たないという分かりやすいケースですが、勤務医と開業医の違いによる失敗事例もあります。
勤務医であれば診療業務に専念できるわけで、多くの医師が目指したと思われる「理想の医療」だけを考えられるのに比べ、開業医であれば経営のことなど考えるべきことが大幅に増えてしまいます。
医師としてクリニック開業を考えるのなら、今一度「医師を志した」ときの自分を振り返ることが必要です。
よくある開業失敗の事例
開業医が失敗する事例には様々なケースがありますが、多くの場合いくつかの類似点が見受けられます。
失敗する主な理由を列挙すると、以下のような問題に集約されるでしょう。
これらの問題を掘り下げていくと、付随する様々な落とし穴が見えてきます。
そこで、ここから先はそれぞれの問題について、失敗の落とし穴を避ける具体的な方法について考えてみましょう。
市場調査とニーズ分析はしていますか?

クリニックを開業するにあたり、事前に市場調査を行いニーズ分析することは、失敗しないための第一歩といえる重要なポイントです。
では、市場調査とニーズ分析はどのように進めていくものなのでしょうか。
基本的な考え方と、的確に開業準備するための進め方について考えてみましょう。
市場調査の方法
クリニックの開業にあたって多くの場合実施されているのが「診療圏調査」といわれるものです。
この診療圏調査とは、ある場所に開業した場合「1日あたり何人の患者様を見込めるのか?」を予測するための調査となります
調査もせずに開業し患者様が思ったように来なければ、その瞬間失敗へのカウントダウンが始まってしまいます。
診療圏調査は、開業予定地を中心とした診療圏を設定するのですが、診療科目によって診療圏の広さは異なり、概ね以下のような考え方が定石です。
一般内科など急な体調不良などの患者様へ対応する診療科は、近くのクリニックが選択されるので、都市部であれば駅から徒歩3分圏や半径1km圏内となります。
一方、精神科や耳鼻科など特定の患者様を診る診療科では、一般内科より広い診療圏を設定します。
診療圏の設定を適切に行えば、次に診療圏の人口とその構成割合など分析していきますが、場所によっては昼間人口と夜間人口に大きな差が見られます。
また診療科目によっては、域内人口の年齢構成などもしっかり調査しなければ、正確な情報にはなりません。
考えるだけで骨の折れる作業ですが、勤務しながらこのような調査をご自身で出来るでしょうか?
オンライン形式で1on1のセミナーを随時開催しているので、お気軽にご利用ください。
ニーズ分析の重要性
クリニックを開業してから安定した集患を目指すのなら、ターゲットとなる患者様と診療圏の人口における年齢構成がミスマッチしていないか、詳しいニーズの分析も欠かせません。
ここで重要になるのは、現在の人口動態だけではなく将来の推計も考慮する点です。
クリニックを開業すると、長い期間にわたり同じ場所でクリニック経営をすることになりますよね。
つまりクリニックを経営する長いスパンで、その診療圏における患者ニーズを予測することが不可欠です。
この点についても、medi-tax株式会社には多くの分析ノウハウを蓄積しているので、医師の皆さんの開業地選びに必ずお役に立てます。
【財務計画の策定】経済的失敗を防ぐ
クリニックの経営も一般事業と同じように税務計画が極めて重要で、無計画で支払いに窮する状態は失敗そのものです。
一般的にクリニックを開業するときは、内装工事や医療機器の購入など多額の初期投資と、軌道に乗るまで安定的に運営するための運転資金が必要になります。
開業のため融資を受けるケースも多いので、財務計画や事業計画の基本を押さえておきましょう。
初期投資と運転資金の計画
クリニックを開業するときの初期投資は、どの診療科目で開業するかによって大きな違いが見られます。
また大都市圏と地方都市との違いや、開業する物件が所有するのか賃貸なのかでも全く異なるでしょう。
賃貸物件で開業するにしても、以下のような支出が開業前に必要になるので、入念な資金計画が必要です
クリニックを開業するとき、陥りがちなのが過剰な設備投資による失敗で、初期投資はいくらでもかけられることに注意が必要です。
また、開業前に掛かる費用だけではなく、運転資金も余裕を持たないとすぐに行き詰ります。
開業直後から予想以上の患者様が来たとしても、保険診療の収入は2か月後にならなければ入ってきません。
運転資金の枯渇は、クリニック経営失敗の一番分かりやすい状況なので、いかに資金計画が大切なのか理解できるでしょう。
収益モデルと財務予測
クリニックの事業計画において重要になるのは、「クリニックの経営コンセプト(理念)」を明確にして、「収益モデル(収益計画)」と「財務予測(資金計画)」の策定をすることです。
収益モデルの作成は、事前に予測していた1日の患者数をもとに、収入を見積もります。
さらに収入によって変わる薬剤費などの変動費や、家賃・人件費といった固定費を計算し、収入が支出を上回る計画でなければ経営が成り立ちません。
また収益モデルとは別に財務予測を考えておくことは、クリニック経営の基本です。
収益モデルで出た利益予想と、お金の出入りは一致することがないので、資金繰表などの財務予測はお金に窮しないため絶対に必要になります。
特に開業から軌道に乗るまでの計画は極めて重要なので、プロの助言を受けながら慎重に考えましょう。
【適切な立地の選定】アクセスと集患の最適化

市場調査やニーズ分析と重なる部分もある内容ですが、クリニックを開業する立地条件は経営の成否を決める重要なポイントです。
そこで考えなければならないのが「クリニックへのアクセス」と「患者の最適化」という2つの要素になります。
そこで、この2点を踏まえた適切な立地の選定について考えてみましょう。
立地選定のポイント
診療科目によってターゲットとなる患者層は違ってきますが、そのターゲット目線でクリニックへのアクセスを考えることが必要です。
患者様から見て「行きやすい」立地は、集患するための大切な要素ですし、きめ細かい分析が求められます。
一つ極端な例を挙げれば、精神科に通う患者様は「通っていることを見られたくない」というニーズがあるため、目立たないような立地が好まれます。
また、実地に開業予定地を見ることで、診療圏調査だけでは分からない事実が判明することもあるでしょう。
患者様から見て「行きやすい」立地は、集患するための大切な要素ですし、きめ細かい分析が求められます。
同じような地点であっても、地域住民からの認知度は大きく変わることがあり、集患力に大きな差が出てしまいます。
医療ニーズが高い地域であっても、理論値だけでは測れない要素があることに留意しましょう。
集患力を高める立地戦略
クリニックの立地で重要なポイントは、いかに集患力を高めるかということですが、理論でいえば医療ニーズが診療機関数を上回っていれば多くの集患が望めます。
つまり診療圏におけるライバルクリニックの把握と分析は、極めて重要なポイントです。
また地域住民や通行人からの認知度も意識した立地戦略が必要で、例えば同じビルだったとしても1階の認知度に比べ2階以上に開業した場合は、半分以下の認知度になると言われています。
集患力を図る指標は多いので、「何となく」ではなくしっかり理論だった立地戦略が重要なのです。
【マーケティングとブランディング】クリニックの差別化
現代ではクリニック経営にも、マーケティングとブランディングの導入は必要不可欠なポイントです。
良い医療を提供していれば患者様は自然に増えていくという待ちの姿勢では、激しい競争を勝ち抜くことができません。
そこでクリニック経営における、マーケティングとブランディングに必要な要素を考えてみましょう。
効果的なマーケティング戦略
クリニック経営におけるマーケティングとは、患者数を増やし収入を増やすために行う施策全般を指します。
広告を出すことで集患を目指すこともマーケティングの一つですが、それだけではなく患者満足度を高めて再来へ結びつけるところまで総合的に考えることが必要です。
第一段階のマーケティングは、市場を分析しターゲットを明確化し、ライバルとの立ち位置の違いを可視化していきます。
また、開業してからも集患マーケティングを継続しながら、患者満足度などを正確に把握しなければなりません。
つまり質の高い医療はもちろん、スタッフの接客態度や院内のインテリアなど、全てがマーケティングに結びつくものだと考えましょう。
最近では、SNSやホームページ開設などウェブを活用したマーケティングも一般的になったので、様々な媒体の活用が考えられます。
ブランディングの重要性
クリニックを開業するとき、誰もが同じ診療圏内にあるライバル医院のことが気になるものです。
患者満足度を高めクリニックの特徴を出すために、ブランディングを行うことが効果的といえます。
クリニックにおけるブランディングとは、診療科目におけるユーザーの想起を促すための施策で、クリニックの経営コンセプトと密接に関わるものです。
マーケティングと重なる点は、患者満足度を高めることで、イメージアップはブランディングの重要なポイントとなります。
地域で「〇〇科といえば〇〇クリニック」と思われるようになれば、間違いなく集患数が増えるでしょう。
【運営体制の構築】スムーズな日常業務への準備
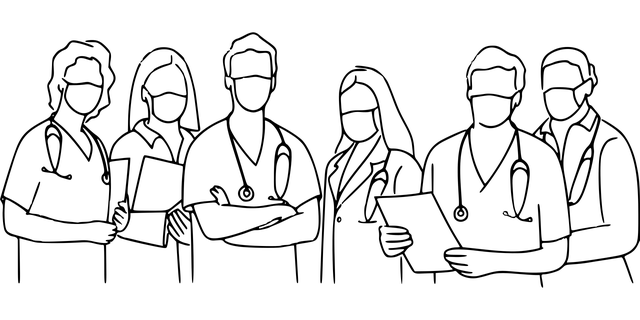
クリニックの開業へ向けて最終段階に近づいてくると、実際に開院したときにスムーズな日常業をできる運営体制の構築が必要になります。
クリニック開業時、運営体制に不備があるとせっかく来院してくださった患者へ悪印象を与えてしまい、大きなマイナスイメージに繋がってしまいます。
そこで、考えておくべき運営体制のポイントを押さえておきましょう。
効率的な運営体制の設計
クリニックの運営体制で大切なポイントは、想定される患者数に効率的に対応できるオペレーション設計です。
来院される患者は、すでに他のクリニックで受診経験があるはずなので、比較されるという自覚をもって考えましょう。
受付から診察を終え、会計を済ませるまでの流れや看護師による処置など、一連の流れで一部に負荷が多かったり、ぎゃくに手を余すようだったりの体制では効率的とはいえません。
もちろん、開業して一定期間が過ぎれば見えてくるはずですが、そんな悠長な考えでは失敗の落とし穴にはまってしまいます。
このようなオペレーションについても、経験の豊富なコンサルタントであれば適切なアドバイスをしてくれるでしょう。
従業員管理とトレーニング
開業時にはスタッフが揃っていなければ開業できませんが、頭数が揃えば良いというものではありません。
新規の開業であれば、看護師などキーになるスタッフには経験豊富な人材を採用することがオススメです。
開業当初は思わぬトラブルなど起こりがちなので、経験の浅いスタッフばかりだと結果的に院長たるあなたの負担が増すばかりになります。
また一般のスタッフにしても、規模の小さなクリニックであれば一人が雰囲気や患者様へ与える印象に大きな影響を与えるものです。
開業の1か月前までにはスタッフ体制を確立し、本番に向けたトレーニングを開始しましょう。
ロールプレイングのなかで、設備や動線の不備が見つかることも多いので、重要な準備です。
これからの時代は、人手不足が深刻になると予想されているので、待遇面を含めた従業員管理も軽視できないポイントになります。
人の入れ替わりが激しくなると、クリニックの評判にも関わってきますので、専門家の知見を含めた検討が必要です。
【リスク管理と対策】予期せぬ問題への備え
クリニックの経営にはリスクは付きもので、勤務医時代との大きな違いは「最終責任者があなた」だということです。
リスクを考えることはストレスを感じることですが、リスクマネジメントを怠るとより大きなストレスを受けることになります。
そこで、クリニック経営におけるリスク管理と対策について、考えてみることにします。
リスク管理の基本
個人でクリニックを開業して考えられるリスクは、以下のようなものが挙げられます。
リスク管理の基本は、これらの事態が発生したことを想定し、それに対する備えをしておくことです。
例えば「もしケガをして2ヶ月入院することになったら」と考え、考えられる対策は「生命保険」や「所得保障保険」への加入でしょう。
考えられる多くの事態には、保険でリスクヘッジできるので、リスクを想定したうえで専門家のアドバイスを求めましょう。
ただ、クリニック開業で最大のリスクは「事業の失敗」なのですが、それを避けるポイントについては最後にお伝えします。
緊急事態対応計画
現在あらゆる業種において、緊急時における事業継続計画(BCPと呼ばれます)の策定が求められるようになりました。
これは、地震などの大規模災害の発生時や、テロ被害の発生、さらにコロナ感染症のようなパンデミック時に、事業をどのように継続していくか計画を立てることを指します。
クリニックの場合は、このような非常時であっても医療提供を求められるので、事態の深刻度に応じて考えなければなりません。
特に重要なのは、医療提供機能の確保と優先順位の明確化で、全部を盛り込むことは不可能だと理解しましょう。
実際に大地震が発生すると、スタッフやその家族の安全確認など、事業継続以前にすべきことが多くなります。
この策定にあたっては、専門家の意見だけではなく、スタッフの意見も反映させることが重要になってきます。
最後に
クリニックの開業を考えた場合、そこへ至るまでにする作業は膨大な量になり、とても一人で進められるものではありません。
今回は「クリニック開業の失敗の落とし穴を避ける方法」にテーマを絞り解説しましたが、そのためには多岐にわたる専門知識が必要なことがご理解いただけたでしょうか。
個々の専門家に依頼していては全体像が見えなくなるので、全てを網羅した助言こそが失敗しないためのコツです。
その点でいえば、medi-tax株式会社にご依頼いただけたら、必要な全領域に専門的知見を踏まえたアドバイスをおくることが可能です。
まずは、お時間のある時にmedi-tax株式会社の無料相談を受けられることをオススメします。
その中で必ず開業へ向けたヒントを得られるはずです。最初の一歩として気軽にご相談ください。











